だいぶ前に買ったまま積読になっていたのを読み始めた。
読書メモ
80歳くらいまで生きるとして、あなたの人生は、たった4000週間だ。
1ページ
ところが現代の、いわゆるタイムマネジメントというやつは、あまりにも偏狭すぎて役に立たない。タイムマネジメントの指南書が教えることといえば、いかに少ない時間で大量のタスクをこなすかだったり、いかに毎朝早起きして規則正しく過ごすかだったり、あるいは日曜日に1週間分の食事をまとめてつくりましょうということだったりする。
3ページ
単に昔のほうが時間の流れがゆるやかだったとか、当時の農民がのんびりしていたという話ではない。違いはもっと根本的なところにある。当時の人たちは、時間を抽象的な存在として体験していなかった。つまり「時間というもの」が存在しなかったのだ。ありえないと思うかもしれない。でもそれは、現代的な時間の捉え方にどっぷり浸かっていて、それ以外の捉え方がうまく想像できないせいだ。ちょうど水の中を泳いでいる魚が、水の性質を理解できないのと同じだ。
22-23ページ
夕暮れどき、クマやオオカミにまぎれて、森の中でささやく精霊の声。畑を耕しながら、ふと広大な歴史の渦にのみ込まれ、遠い祖先が我が子と同じくらい身近に思えるひととき。作家のゲイリー・エバリーの言葉を借りるなら、「あらゆるものが充分にあり、自分や世界の空虚さを埋めなくていい、そんな領域に突然入り込む」瞬間。そんなとき、自分と世界を隔てる境界線は揺らぎ、時間は静止する。「時計が止まるわけではないが、時を刻む音がふいに聞こえなくなる」とエバリーは表現する。祈りや瞑想でそんな境地に達する人もいれば、壮大な風景のなかでふと出会う人もいる。
25ページ
 カノ
カノこの「深い時間」という感覚はわからないでもない。確かに日々のタスクをこなしている中では味わえない。僕の場合は旅行中に感じることがある。
農民の仕事に終わりはない。次の日になれば乳を絞り、次の収穫期が来れば収穫する。だから、すべて完了した状態というのはありえないし、ゴールを決めて競争する意味もない。歴史家はそんな生活様式を「タスク中心型」と呼ぶ。抽象的な時間軸ではなく、タスクそのものが有機的に生活のリズムを生みだすからだ(ちなみに、中世の生活はゆっくりしていたと思われがちだけれど、実際には「ゆっくりとした生活」という言葉自体が意味をなさなかったというほうが正しい。そもそも、何とくらべてゆっくりなのか?)。
24-25ページ
産業革命は一般に、蒸気機関の発明によって起こったといわれる。だがルイス・マンフォードは1934年の大著『技術と文明』で、おもしろいことを指摘している。産業革命は、時計なしではけっして起こらなかったというのだ。
27ページ
ところが今を犠牲にしつづけると、僕たちは大事なものを失ってしまう。今を生きることができなくなり、未来のことしか考えられなくなるのだ。つねに計画がうまくいくかどうかを心配し、何をやっているときも将来のためになるかどうかが頭をよぎる。いつでも効率ばかりを考えて、心が休まる暇はない。あの「深い時間」、時間の物差しを捨ててリアルな現実に飛び込んでいくときの魔法のような感覚は、もうどうやっても手が届かない。
30ページ
さらに一歩進んで、時間を「使う」という考え方自体を疑ってみることもできる。そもそも時間は、自分の持ち物ではない。時間を使うかわりに、時間に使われてみたらどうだろう。計画通りにスケジュールをこなす人生ではなく、歴史のなかの現在に身を置き、その時々の必要に応えて生きてみるのはどうだろうか。
38ページ

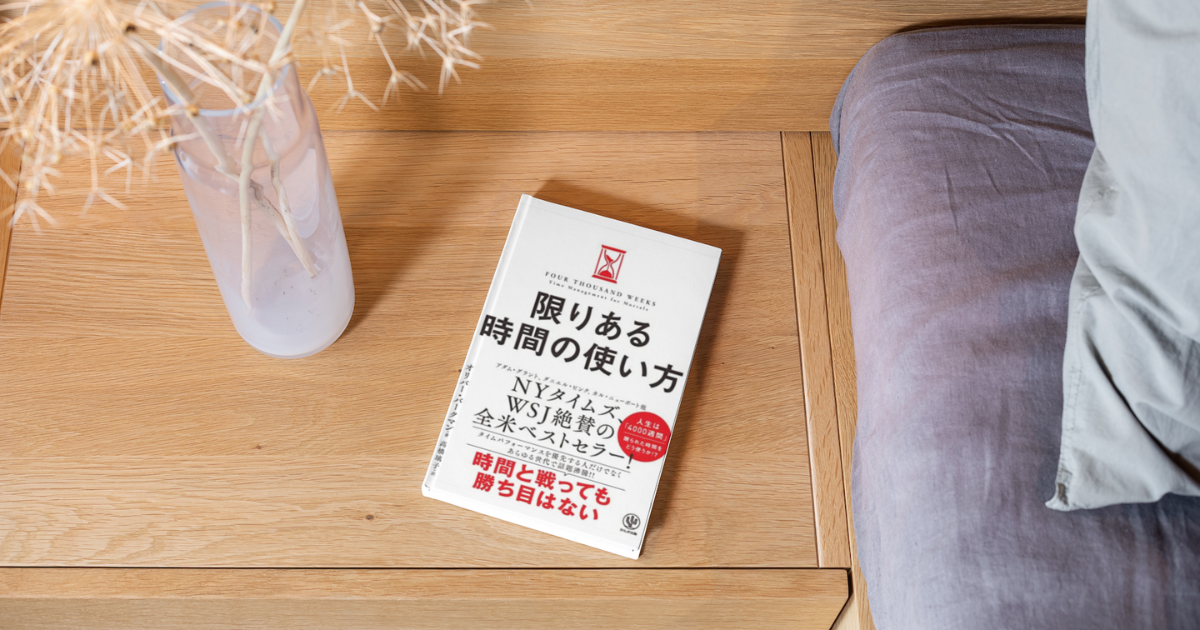

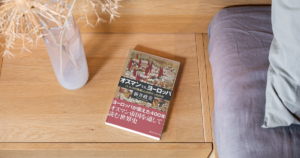

コメント